


単にお金を得るための副業ではなく、自分が楽しむだけの趣味でもない。 ベクトルを社会に向けて、一人ひとりが大切にする価値観を表現し、
社会のこれからを創っている。そんな人たちが持っているもの、それが2枚目の名刺。
企業で働きながら、会社外で自分の経験やスキルを活かしてNPOの取り組みを後押しすることも、社会にイノベーティブな価値を創ることに
会社の外で挑戦することも、子育て中の人が自分でプロジェクトを立ち上げることも、地域の活動にこれまでとは違う視点を持ち込み
盛り上げることも、そして学生や子どもたちが未来を自分たちの手で作ろうとする取り組みも。「こんな社会になったらいいな」を創るとき、
社会に対する傍観者でなく当事者として、自分と社会とこれまでとは違う関わり方ができること、それを実行しようとする
誰しも持つことができるもの、それが2枚目の名刺。
2枚目の名刺を持つことが当たり前の選択肢となり、今いる組織や立場を超えて、これまでの枠組みにとらわれることなく、 「こんな社会になったらいいな」というマイミッションを実現するストーリーがあふれている未来を実現します。

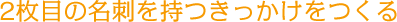




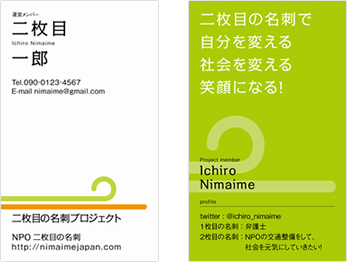

私自身の「2枚目の名刺」は今まで大きく2つの展開があります。

2009年8月、私は留学先で同級生4人とコンサルティングプロジェクトに取り組んでいました。
テーマはベトナム商工会議所からの依頼で
「ベトナム農産物の対日輸出促進策を考えること」。
当時は金融業界で働きながらも食料分野の未来にも関心を持っており、
未経験分野ではありながらも挑戦してみたものでした。"学生"という名刺だけを持ち、
会社の名前に頼ることなく勝負するその環境の中で、多くの失敗や苦労を積み重ねました。
プロジェクト完了後クライアントであるベトナム関係者より「これで次の一手につながる」と
いってくれた時確信したことがあります。
「本業の仕事の外でも自分が生み出せる価値がある」
「ここでの多くの失敗は間違いなくこれからの自分の力になる」

そして、このプロジェクトを通して出会った人たちに、「2枚目の名刺」に繋がるイメージや概念となる言葉を投げかけてもらいました。「君はこのまま日本に帰って会社員をやるだけで本当にいいのか?」「ベトナムは若い力にあふれている。日本はどうだ?もっと日本にできることはないのか?」と、あるベトナム人起業家から声をかけられたこと。
「都会の子どもたちにも、田舎でのびのびと遊ぶ経験をしてもらいたいんです」。ある金融機関の役員が、山梨の農家を「田舎暮らしの家」として改修し、ここを拠点に子どもたちに農作業や自然の中での遊びを体験させる活動をしていると話し、彼から本業以外のもう1枚の名刺をもらったこと。自分以外の人間のために何かを成し得ていること。自分や組織のことだけではなく「社会」をどうしていきたいかという視点。会社以外のもう1つの名刺を見ながら理屈抜きに「かっこいい」と思ったこと。この2つの出会いは私にとって偶然の出会いにしかすぎなかったはずです。でもその出会いが「2枚目の名刺」のコンセプトに関わる原点でもあります。
本業の傍ら、もう1枚の名刺を持つくらい本気で自分の思いを形にしていく。もっとたくさんの人たちがこうした経験を当たり前のようにできるようにならないか。どうやったら、日本で広げていくことができるだろうか。そんな話がイギリスのすし屋で留学を共にした同級生たちと一気に展開し、構想を書き留めた1枚の紙はあっという間に埋まっていきました。これがNPO法人二枚目の名刺が生まれた瞬間でした。



NPO二枚目の名刺を立ち上げた2009年、会社生活8年目の 30歳。
私は本業とは別の「2枚目の名刺」として「NPO二枚目の名刺」で社会に変化を仕掛けることを選びました。
当時私には2歳の娘がいました。娘が生まれた頃から幾度となく自分に問うことがありました。「娘が生きる未来の社会はどんな風になっているのだろう」未来は今しか創ることができなくて、今、もし何もしなかったら、未来は後悔することになるかもしれない。
しかし、一人の力で何かをやろうとしても、それには限界がある。もっと周りの人たちに変化のきっかけを起こし、未来を共に創りたいと思う人たちが一層活躍できるように後押しすることができれば、その変化のスピードを早められるだろう。今NPO二枚目の名刺の活動を行なっているときの土台になるような考え方ができ始めました。
娘が大きくなった時「パパがやってきたことカッコいいね、私たちの今に繋がっているんだね」と言われるようなことをしていたい、という想いと勢いに背中を押されましたが、自分から見える社会の視点ではなく、次世代から見える社会の視点に切り替わったのは、私自身にとっても大きな変化でした。立上げから8年がたった今、2枚目の名刺という選択肢は、個人から企業も巻き込み拡大しています。そして、2枚目の名刺をもつ社会人が活躍するストーリーは、多様でカラフルなものになってきています。私自身も、普通の会社員としての本業を持ちながら、4人に増えた娘の子育てをしながら、どこまで社会に刺激と変化を届けられるか、挑戦は続きます。
本業で持つ1枚目の名刺のほかに、社会を創ることに取組む個人名刺を"2枚目の名刺"と位置づける。NPOと社会人をつなぎ、社会人の変化・成長を促すことで、ソーシャルセクター、企業の発展を同時に後押しするモデルを提唱。現在、新しい働き方、人材育成のあり方として、企業、行政、アカデミア等多方面から注目。2009年二枚目の名刺立上げ(2011年NPO法人化)、商社勤務の傍ら自らも2枚目の名刺としてNPO代表を務める。4児の父。慶應義塾大学卒業、Oxford 大学Said Business School MBA、2002年日本銀行入行、金融機関・金融市場モニタリング、経済調査等を担当。この間、2005~2007年に、経済産業省に出向し金融制度設計に取組み。2014年より、商社にて食料部門の海外事業開発・投資を担当。